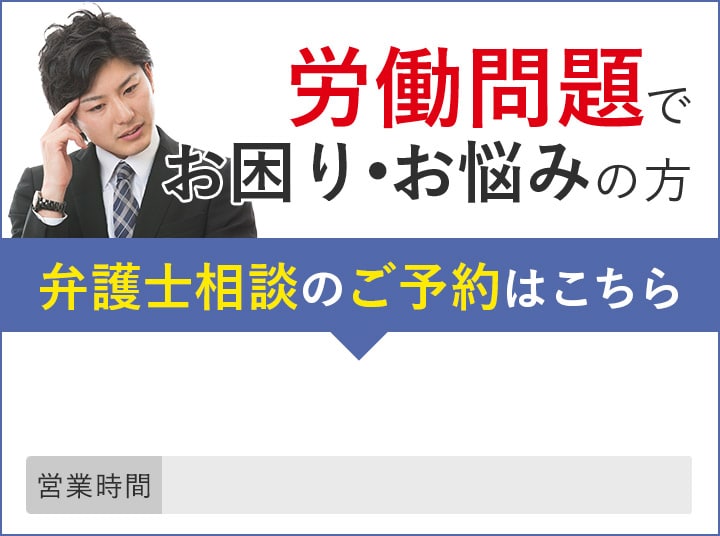管理職でも残業代を請求できる? 可能なケースとその方法を弁護士が解説
- 残業代請求
- 残業代
- 管理職
- 新宿
- 東京

東京労働局の統計によると、令和元年度の東京都における労働基準監督署などへの総合労働相談件数は15万6858件にのぼりました。
労働問題は、一般の従業員だけでなく管理職として働く場合にも当然生じうるものです。たとえば、管理職であることを理由に、会社から残業代を支払ってもらっていない方も少なくありません。
しかし、管理職の方でも、残業代の支払いを請求できる場合があります。本コラムでは、管理職の方が残業代の支払いを請求できる場合とその請求方法を、ベリーベスト法律事務所 新宿オフィスの弁護士が解説していきます。
1、管理職とは
「管理職」という言葉は、一般的に、組織の責任者を意味します。どういった役職を管理職として扱うかは会社によって異なりますが、課長や部長、マネージャーなどといった役職を管理職と呼ぶことが多いでしょう。
しかし、一概に管理職といっても、労働基準法が定める「管理監督者」に当たるかどうかで、労働時間などの規制に大きな違いが生じます。
そして、管理監督者に当たる場合は、残業代の支払いを請求することはできませんが、管理監督者に当たらない場合は、請求することができるのです。
したがって、会社から「管理職だから残業代は支払わない」と言われていたとしても、実際には管理監督者に当たらない場合、残業代は支払われるべきものといえます。
2、管理監督者とは
「管理監督者」とは、労働条件の決定やその他労務管理について経営者と一体的な地位にある者をいいます。
管理監督者に当たるかどうかは、役職名にとらわれず、実態に即して総合的に判断されます。具体的なポイントは以下の3点です。
●職務内容や権限および責任に照らして、労務管理を含め企業全体の事業経営に関する重要事項に関与しているか
●勤務態様が労働時間に対する規制になじまないものか
●基本給や役職手当などの給与や一時金において管理監督者にふさわしい待遇がされているか
これらのポイントと合致しない事情が認められる場合、管理監督者に当たらない可能性があります。たとえば、ファストフード店の店長が残業代の支払いを求め、管理監督者に当たるかどうかが争点となった事例では、①店長の職務や権限があくまで店舗に関するものであって企業全体に関わるものではなかったこと、②店長の労働態様に自由な裁量がなかったこと、③店長の待遇が労働基準法上の規制の適用外を妥当とするには十分でなかったことなどの事情から、管理監督者に当たらないと判断されました。
このように、管理監督者に当たらないにもかかわらず、そのように扱われている方のことを、一般的には「名ばかり管理職」ともいいます。
その一方で、管理監督者に当たる場合、経営者と一体となって仕事をしているとみられるため、一般の労働者とは異なる扱いを受けることになります。
3、管理監督者に該当する場合はどうなる?
管理監督者に当たる場合に、残業代との関係で、特に押さえておきたいポイント4点をみていきましょう。
-
(1)労働時間の規制が適用されない
原則として、使用者は、労働者を1日8時間、1週間40時間を超えて労働させることができません(労働基準法32条)。この労働時間の限度を「法定労働時間」といいますが、法定労働時間を超えて労働者を労働させた場合、使用者は、残業代として、割増賃金を支払わなければなりません。
また、法定労働時間内の労働にとどまったとしても、就業規則で定められた労働時間を超えて労働させた場合、使用者は、残業代として、所定賃金を支払わなければなりません。
しかし、管理監督者に対しては、労働時間に関する労働基準法の規定が適用されません。
したがって、管理監督者は、時間外労働をしたとしても、残業代の支払いを請求できないことになります。 -
(2)休憩時間に関する規定が適用されない
使用者は、労働時間が1日6時間を超える場合には少なくとも45分、1日8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません(労働基準法34条1項)。
しかし、管理監督者に当たる場合には、休憩時間に関する規定が適用されません。
したがって、管理監督者に対しては、必ずしも休憩時間を与える必要はないという扱いがされることになります。 -
(3)休日に関する規定が適用されない
使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1日または4週間に4日以上の休日を与えなければなりません(労働基準法35条)。
しかし、管理監督者に当たる場合には、休日に関する規定が適用されません。
したがって、管理監督者は、休日労働をしたとしても、その分の残業代として、休日手当の支払いを請求することはできません。 -
(4)深夜手当は支給される
前述したように、管理監督者は、残業代や休日手当を支払ってもらうことはできません。
ただし、管理監督者であっても、深夜労働をした場合には、一般の労働者と同様に深夜手当が支払われます。ここでの「深夜」とは、原則として、午後10時から翌日午前5時までの間をいいます(労働基準法37条4項)。
まずは、給与明細を確認してみてください。深夜労働をしているにもかかわらず、深夜手当が支払われていなければ、会社に対してその支払いを請求することが可能です。
4、管理職が残業代の支払いを請求する方法
管理監督者に当たらない管理職の方や、深夜手当が支給されていない管理監督者は、次のような方法で、会社に残業代の支払いを請求することができます。
なお、残業代の支払請求権は、原則として、その残業代が支払われるべきであった給与日から2年で時効により消滅してしまうので、注意が必要です。ただ、労働基準法の改正により、令和2年4月1日以降に支払われるべき残業代については、当分の間、時効期間が3年に延長されます。
-
(1)内容証明郵便で会社に請求する
残業代の支払いを会社に請求する場合、タイムカードなどの証拠にもとづいて、残業代の額を計算する必要があります。残業代の額を算出したら、会社と交渉してその支払いを求めましょう。
会社に残業代の支払いを請求する際には、日本郵便が取り扱う内容証明郵便で送付する方法が有益です。内容証明郵便は、会社に残業代の支払いを請求したことを示す有益な証拠となります。また、残業代の支払請求権が時効により消滅してしまうことを防ぐ役割もあります。
なお、弁護士に依頼した場合は、弁護士が内容証明郵便を送付し、交渉を進めます。弁護士の介入は、会社側にとって大きなプレッシャーになり、早期に会社が残業代の支払いに応じる効果も期待できるでしょう。 -
(2)労働審判で解決する
会社との交渉がまとまらない場合などには、裁判所に労働審判を申し立てることもできます。労働審判は、裁判官と労働審判員を交え、労働者と会社側との話し合いにより紛争解決を目指す手続きです。原則として3回以内の期日で審理は終わり、話し合いがまとまらなければ審判という結論が下されることになるので、訴訟よりも迅速に解決を図ることが可能です。
ただ、労働審判の申し立ては、時間との勝負になってきます。第1回の期日までにすべての主張と証拠を準備したうえで、会社からの反論などに備えなければならず、時間的にも心理的にも大きな負担となります。申し立てに必要な作業は、専門的知識を持つ弁護士に任せることも、選択肢のひとつでしょう。
審判が確定した場合には、審判調書が作成され、会社側に差押えなどの強制執行をすることも可能です。もし審判に対して不服があり当事者から異議が出た場合には、通常の訴訟に移行します。 -
(3)訴訟で解決する
労働審判に対して異議が出た場合には、訴訟で解決することになります。また、労働審判を経ずに訴訟を提起して解決することも可能です。
訴訟では、争点に関して当事者双方が主張立証・反論を行い、裁判所はその争点に対する判決を言い渡します。訴訟への対応は、交渉や審判への対応にも増して専門的知識が求められますので、弁護士への依頼を特におすすめします。
5、まとめ
本コラムでは、管理職が残業代を請求できる場合とその請求方法を解説していきました。
管理職とされていても、労働基準法上の管理監督者に当たらない場合には、残業代を請求できます。また、管理監督者に当たる場合でも、深夜手当は請求することが可能です。
残業代を請求する方法には、内容証明郵便などを利用して会社に直接請求する方法と、裁判所に対して労働審判を申し立て、または訴訟を提起するという方法があります。まずはベリーベスト法律事務所 新宿オフィスの弁護士に、お気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています